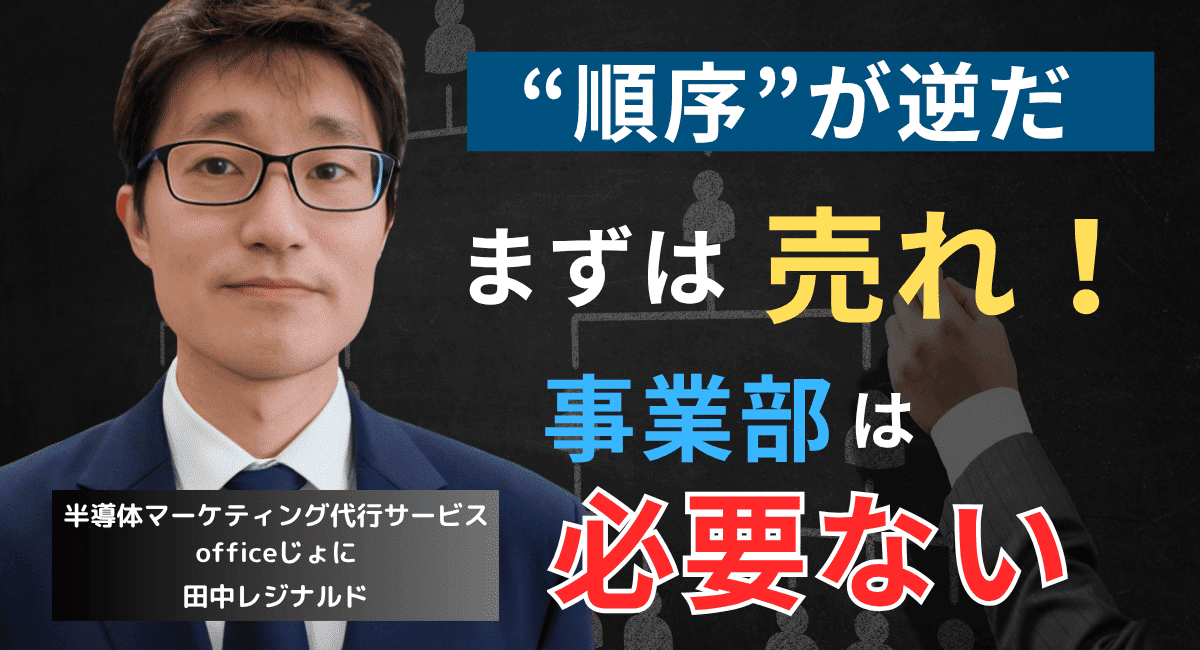もしあなたが──
「新製品を出すなら、まず事業部を立ち上げるべきだ」
「工場が稼働できる状態になってから、製品販売を始めるのが正しい」
「事業部がなければ、新製品に対する熱量が顧客に伝わらない」
──そう考えているのなら、
あなたは昭和の営業モデルに毒された、“時代遅れの経営者”である。
今どき、売れるかどうかも分からない製品に対して、
「部長職を設けて、専任チームを組んで、部門予算を確保して──」
そんなふうに、万全の体制を整えること=成功への近道だと思っていないか?
残念だが、それは完全な間違いだ。
むしろその考えこそが、
失敗が許されない“身動きの取れない組織”を、自ら作り出す元凶である。
そして、そういう会社に限って、決まってこうなる。
・部署の人員だけが増え、成果はゼロ
・「予算を取った手前、やめづらい」という空気が、社内を支配し始める
・売上が低迷しても、ずるずると継続してしまう
つまり、あなたが新たな事業部を立ち上げたその瞬間から、
“後戻りできない道”へと足を踏み入れてしまっているのだ。
これはもはや、“経営判断”ではない──「自爆スイッチ」である。
売れなかった時の、“地獄の請求書”を見たことがあるか?
なぜ、製品が売れる前に事業部を作ってはいけないのか?
答えはシンプルだ。
失敗したときのダメージが、あまりにも大きすぎるからである。
失敗は、ビジネスの宿命だ。
だが、「事業部」という“組織のカタチ”を先に作った瞬間──
その失敗は、「現場担当者の問題」では済まなくなり、
「経営判断ミス」として、会社全体の責任に格上げされてしまう。
つまり、誰も責任を取りたがらない
“社内政治の舞台”が幕を開けるのだ。
さらに深刻なのは、
「売れなかったとき」の撤退コストである。
たとえば──社員1人の平均年収が500万円。
事業部に5人配属していたら、
それだけで年間2500万円の人件費が飛ぶ。
それだけではない。
・製造ラインの追加工事
・専用設備の購入
・工場スペースの改修
・販促資料・広告の制作
・社員の配置転換
・それに伴う“調整・会議・根回し”
こうした“目に見えないコスト”が、会社を静かに蝕んでいく。
そして忘れてはならないのが、配置転換前の「待機期間」だ。
社員の新しい配属先が見つかるまでの、
“やることがない時間”もまた、立派な損失である。
こうした積み重ねが、やがて赤字部門の温床となり、
会社のキャッシュフローをじわじわと悪化させていく。
──これが、「製品が売れる前に事業部を作った企業の末路」である。
“売れた証拠”が出てから、初めて部署を作れ
では、どうすればいいのか?
答えはシンプルだ。
まず、売れ。話はそれからだ。
そして、売れたという“証拠”をもとに、
必要最小限の体制で、新たな部署を立ち上げろ。
あなたの会社に今、必要なのは──
立派な事業部でも、複雑に階層化された組織図でもない。
まずは、たった1つのサンプル製品。
そして、既存顧客に渡す1枚の販促資料だけでいい。
それだけで、「市場が反応するかどうか」がわかる。
机上の仮説ではなく、現場で得られた“実証データ”が手に入る。
その“実証データ”とは、たとえばこんなものだ。
✔︎ 問い合わせ数
✔︎ 商談数
✔︎ 案件受注数
──こうした具体的な数字が、
その製品に“需要があるかどうか”をはっきりと示してくれる。
それらのデータをもとに、はじめて事業部を立ち上げればいい。
なぜなら、その時点で「売れること」はすでに確定しているからだ。
確実に売れるとわかっているものに、自社リソースを投下する。
これこそが、“戦略的に勝ち続ける半導体企業”のやり方である。
何度でも失敗できる体制を作れ。それが勝つ企業の条件だ
多くの半導体企業は、「失敗しない体制」を作ろうとする。
だが、その考え方自体が根本的に間違っている。
必要なのは、
「絶対に失敗しない仕組み」ではない。
「何度でも失敗できるシステム」である。
あなたが目指すべきは、以下のような状態だ。
✔︎ 売れなかったら、即撤退
✔︎ 売れたら、即拡張
✔︎ 新製品・新サービスの販売回数を、今の10倍に増やす
つまり、「打率」ではなく「打席数」で勝負せよ。
バッターボックスに立てる回数こそが、あなたの会社の未来を決めるのだ。
この体制があれば──
毎月1件のテスト販売、年に12件の新製品チャレンジも現実になる。
売れなかった製品は、すぐに“捨てる”。
売れた製品だけを、“育てる”。
そうやって、事業部として育成する価値のあるものだけを選び抜くのだ。
そして、こうした取り組みを継続すれば──
数年後には、会社の中で大きな変化が起きているはずだ。
そのときには、「売ってから育てた製品群」こそが、
あなたの会社における“最も利益率の高い製品ベスト3”を占めているだろう。
だからこそ、
「たぶん売れるだろう」という希望的観測ではなく、
「すでに売れた」という実績を根拠に、意思決定せよ。
必要なのは、完璧な準備や、分厚い企画書ではない。
たったひとつの受注。たったひとつの問い合わせ。
その“結果”こそが、最強の事業判断材料となる。
なぜなら、売上という数字は、
「現場で何が起きたのか」を最も正確に映し出すものだからだ。
必要なのは、経営者の直感でもなければ、現場の期待でもない。
顧客が「この製品に金を払った」という事実こそが、
組織としての次の一手を決める、もっとも信頼できる材料なのである。
最後に、はっきりと言う。
まず売ってみろ。
市場が反応した“直後に”部署を作れ。
それこそが──
これからの半導体企業に求められる、
本質的なマーケティング戦略である。