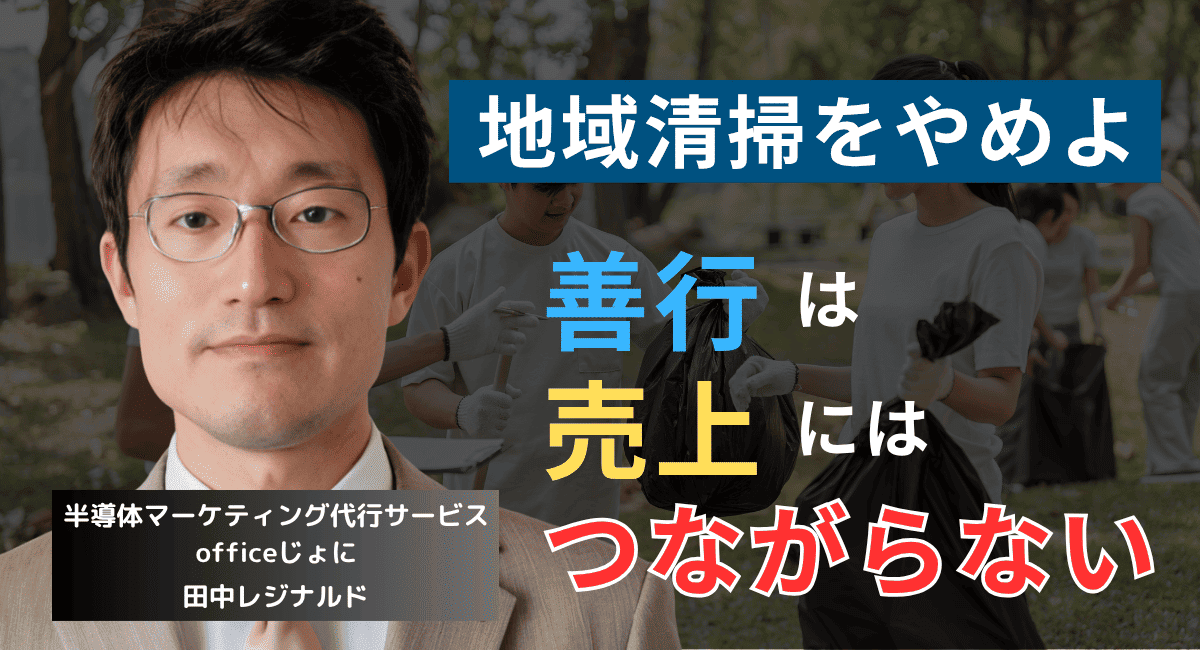もしあなたが──
「地域から愛される企業になれば、自然と売上が増える」
「地域清掃活動が採用にいい影響を与えるはずだ」
「社会貢献こそが企業ブランディングの要だ」
──そう信じているのなら、今すぐこのページを閉じよ。
この先にあるのは、その信念を真っ向から否定する話だ。
ここ数年、半導体業界に限らず、日本中の中小企業が、
「地域清掃」「交通安全」「緑化活動」などの社会貢献活動に打ち込んでいる。
ニュースで取り上げられ、地元の新聞に載り、SNSでも称賛される。
子どもたちから「ありがとう」と声をかけられ、行政から感謝状が届く。
社員たちも、地域貢献活動に手応えと誇りを感じている。
──たしかに、気分はいいかもしれない。
だが、それで満足していいのか?
それで、売上は伸びたのか?
それで、採用者数は増えたのか?
それで、市場競争力は高まったのか?
答えは明確だ。
売上も、採用も、競争力も──ほとんど何も変わっていない。
どれだけ感謝の言葉をもらっても、
売上や採用といった数字には、いっさい反映されていない。
なぜなら──
社会からの“好感度”とビジネスの“成果”は、完全に別のものだからである。
「感じの良さ」だけでは、人も売上も動かない
あなたの会社が目指すべき評価は──
「社員の方が優しくて、いい会社ですね」
「地域に貢献していて素晴らしいですね」
──そんな社交辞令ではないはずだ。
たしかに、そういった言葉は耳障りがよく、心をくすぐる。
だが、そこからは1円の売上も生まれない。
どれだけ褒められても、あなたの会社に応募してくる人は一人として増えない。
本来、企業が目指すべき評価は、たった二つに絞られる。
「この会社から買いたい」
「この会社に入社したい」
──この信頼を獲得できるかどうか、それがすべてだ。
それ以外の賞賛は、ビジネスの世界では何の価値も生まない。
単なる“自己満足”に過ぎず、結果として“お金と時間の浪費”で終わってしまう。
では、現実はどうだろうか?
多くの中小企業が、
地元紙の片隅に掲載された一段記事や、
自治体からの感謝状に満足してしまっている。
だがその裏側では──売上は横ばいのまま。
求人応募もほとんどないという状態が続いている。
なぜ、そうなるのか?
それは、市場が評価の基準にしているのは、
あなたの会社の「人柄の良さ」や「地域への善行」ではないからだ。
評価されているのは、はるかに現実的でシビアなポイント──
「この会社は、どんな価値を提供してくれるのか?」
「この会社は、どれだけ成果を出せるのか?」
「この会社で働くことで、自分はどんな経験や成長を得られるのか?」
つまり顧客も求職者も、会社の印象ではなく、
「どんな価値が得られるのか?」
「どれだけ成果を出せるのか?」
「どんな成長につながるのか?」といった、
ビジネスとしての実力と再現性こそを冷静に見ているのだ。
どれだけ真面目に取り組んでいても、
どれだけ感じのいい対応をしていても──
顧客も求職者も、見ているのは“ただ一つ”。
顧客は問う──「この企業は、自分たちの課題を本当に解決してくれるのか?」
求職者は見極める──「この会社に入れば、価値ある経験が得られるだろうか?」
彼らの判断基準は、驚くほど明快で現実的なのだ。
「この会社と関わることで、自分にとって確かな成果やメリットがあるのか?」
──それだけである。
つまり、問題の本質は──清掃活動による“好感度アップ”ではない。
顧客や求職者が本当に見ているのは、成果につながる仕組みを持ち、
それを実行し続けているかどうかという、企業としての“動かぬ証拠”だ。
そして、それを裏づける信頼に足る実績や日々の行動があるかどうか──
その一点を、顧客も求職者も、静かに、そして確実に見ているのだ。
この現実に背を向けた瞬間、
あなたの会社はこう言われる存在になる。
「たしかに、いい会社だとは思う。けど……選ぶ理由が見当たらないんだよね」──と。
地域清掃で売上は伸びない──「良いことをしている」は錯覚だ
マーケティングの本質は、社会貢献ではない。
「セールスを不要にする仕組みをつくること」
「買う気になった顧客を育てること」──それがすべてだ。
では、地域清掃活動には本当にその力があるのか?
あなたの会社の売上や採用に、どれほどの影響を与えていると言えるのか?
もし、社内でこんな主張をする管理職や社員がいるなら要注意だ。
「地域清掃はやめるべきではありません。売上にも、採用にも良い影響があります」
彼らがそう言うのなら、こう返してほしい。
「ならば、テストしてみよう」
たとえば、明日から毎朝1時間の清掃を100日間やってみる。
その時間と労力の“投資”が、どれだけの成果を生んだか──数値で検証してみるべきだ。
なぜなら、経営とは「どれだけ頑張ったか」ではなく、
「何を得られたか」で評価される世界だからだ。
どれだけ善意があっても、どれだけ清掃に尽力しても、
数字として結果が出なければ意味がない。
地域清掃活動に100万円相当の人件費や時間をかけたとする。
その結果として、何件の問い合わせを獲得できたのか?
どれだけの商談が生まれ、いくつが成約につながったのか?
では、同じ100万円を使って、
ネット広告を出したり、展示会用の動画を制作したらどうか?
どちらが見込客の獲得に貢献するかを比較すれば、一目瞭然だ。
──具体的な例を挙げよう。
✔️ 社員数:10人
✔️ 社員の時給:1,000円
✔️ 毎朝1時間の清掃 × 100日間 = 総コストは100万円
この同額(100万円)の予算を、
たとえば次のような施策に充てていたとしたらどうだろう?
✔️ 展示会用のプレゼン動画制作
✔️ 自社技術を伝えるブログ記事の外注
✔️ Google検索広告による見込客の獲得
どちらが「ビジネスとしての成果」をもたらすか──比べるまでもない。
あなたに成果を出す意思があるのなら、答えはすでに出ている。
ビジネスは善因善果で動く世界ではない
地域清掃活動では、売上は伸びない。
採用にもつながらない。
そして、企業ブランディングにも結びつかない。
なぜなら──
ビジネスの世界は、「善因善果」で動いているわけではないからだ。
どれだけ“いいこと”をしても、顧客はそれだけで製品を選んではくれない。
どれだけ“感謝”されても、それだけで入社を決める人はいない。
マーケティングとは、「やったことに対して、見合う結果を得る」ための活動だ。
つまり、正しい因を打たなければ、正しい果は得られない。
「善行=成果」ではなく、「戦略的な行動=成果」なのだ。
あなたがほうきを手に、街角で汗を流しているその瞬間、
競合は、動画を配信し、広告を出稿し、ブログ記事の更新を繰り返し、
見込み客の頭の中に、自社の価値と存在意義を着々と植えつけている。
戦略なき善行(清掃活動)は、経営資源の浪費でしかない。
今、企業に求められているのは「良いこと」ではない。
勝つための仕組みを持っているかどうか──この一点に尽きる。
あなたの会社の未来を決めるのは、「地域清掃」や「緑化活動」ではない。
“誰に、何を、どう伝えるか”──その設計こそが、成果の分かれ目になる。
だからこそ、
最後にハッキリと言おう。
今すぐ、地域清掃活動をやめよ。
「良いことをしていれば、自然と売上や採用につながる」
──そんな根拠のない希望的観測は、今この瞬間に捨て去れ。
これこそが──
あなたの会社が、10年後も顧客に選ばれ続けるための、
唯一のマーケティング戦略である。