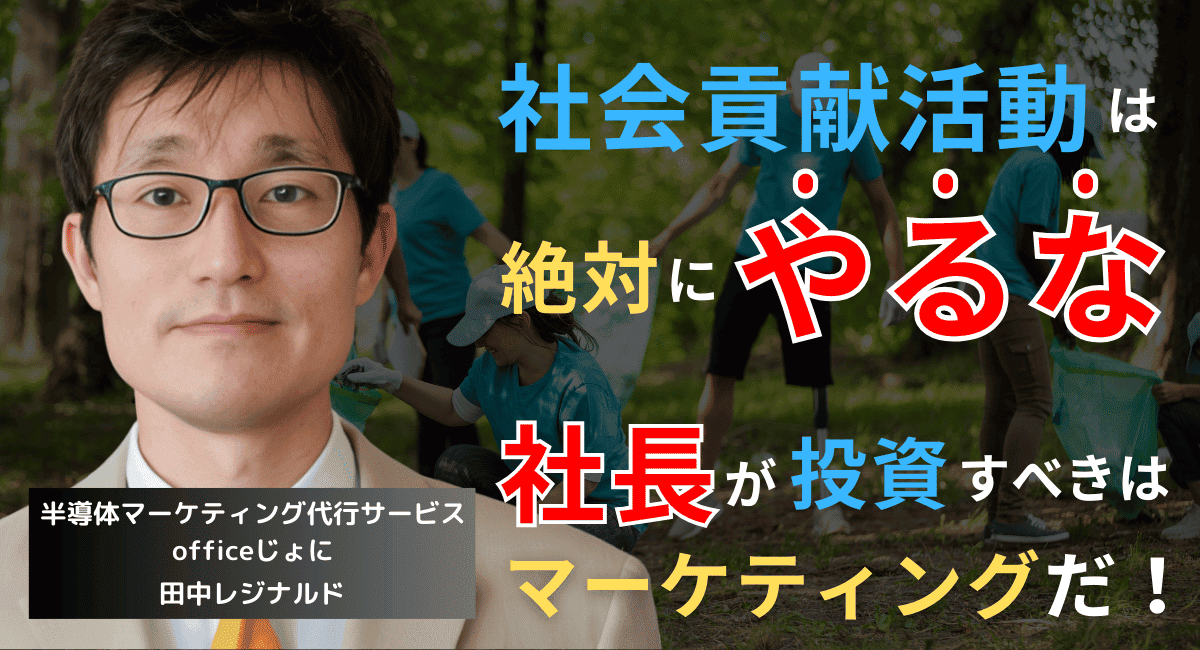いい会社ごっこはやめろ──投資すべきは“マーケティング”だ
もしあなたが、
「うちはCSRに力を入れている」
「SDGsにも積極的に取り組んでいる」
「社会貢献への寄付額は業界No.1だ」
そんなふうに自社の“立派さ”を誇らしげに語っているのなら──
今すぐその思考を捨てろ。
社会貢献では、会社の未来は守れない。
いや、それどころか──
“誤った投資先”を選び続けることが、あなたの会社を静かに、
しかし確実に蝕んでいく。
外から見れば立派に映るだろう。
あなたの家族も、取引先も、地域社会も、
「素晴らしい企業ですね」と褒めてくれるかもしれない。
──だが、その瞬間、あなたの中で“錯覚”が始まる。
「これは会社の未来にとってもプラスになる」
「社会に貢献していれば、きっと何かが返ってくるはずだ」
「弱者に寄り添う姿は人間として、経営者としても正しい」
──そんな根拠のない期待と希望に、無意識のうちにすがってしまう。
だが、現実は冷酷だ。
売上は変わらない。利益も増えない。顧客も増えていない。
にもかかわらず、「でも、いいことをしているから…」と自分を正当化する。
これこそが、“いい会社ごっこ”の正体だ。
そしてそれは、経営者として最も危険な自己欺瞞である。
目次
SDGs、CSRが“正義”とされる時代の落とし穴
ここ数年で、SDGs、ESG、CSR──
いわゆる“社会性のある取り組み”が、企業評価の軸としてもてはやされるようになった。
メディアはこぞって持ち上げ、取引先や自治体も「素晴らしい」「理想的だ」と絶賛する。
──だが、経営の現場にいる人間なら、わかるはずだ。
これは幻想である。
いや、もっと正確に言おう。美化された“罠”だ。
企業にとって、最優先すべき使命は何か?
それは利益を生むことだ。
売上を立て、雇用を守り、継続的に価値を提供し続けること。
それができなければ、どれほど社会に貢献しようと──ただの自己満足でしかない。
社会貢献を優先し、利益を後回しにするというのは、
砂漠に花壇をつくるようなものだ。
確かに、見た目は美しい。
取り組みも立派に映るだろう。
だが、水がなければ3日で枯れる。
水=利益。
その供給が止まった瞬間、会社は終わる。
社会貢献が悪だとは言わない。
だが──“順番”が違う。
まず、生き延びよ。
まず、売上を作れ。
まず、社員に給料を払い続けよ。
そのために今、経営者がやるべきことはひとつだ。
マーケティングに投資せよ。
社会貢献より先に、市場で勝ち残るための武器を持て。
それで本当に、社員が幸せになるのか?
企業として寄付をした。地域イベントに協賛した。
SDGsのバッジをつけて、社内ポスターも作った。
そのたびに、社員たちはこう思うかもしれない。
「うちは、社会に貢献している」
「なんだか、いい会社で働いてる気がするな」
「子どもに誇れる企業で働けるのは最高だ」
──だが、本当にそれでいいのか?
試しに考えてみてほしい。
仮に、毎月100万円をそうした社会貢献活動に投じていたとしよう。
それが年間で1,200万円。社員2人分の年収に相当する金額だ。
あなたは、その1200万円を、“自分の気分の良さ”のために使っている。
それでも、「いいことだから」と納得できるのか?
しかも問題は金額だけではない。
最大の問題は“測れない”ことだ。
「自社の社会的評価をどれくらい高めたのか?」
「どれほどの見込み客獲得につながったのか?」
「全費用に対し、いくらの売上を手にしたか?」
──社会貢献活動は何一つ測れない。
にもかかわらず、
社内外から褒められることで、「やってよかった」と錯覚してしまう。
だが、その称賛は何を生み出す?
売上か?
利益か?
社員の昇給か?
答えはNOだ。
マーケティングと違い、社会貢献には“数値”が存在しない。
数値がなければ、成果が見えない。
成果が見えなければ、改善ができない。
改善できなければ──それは経営ではない。ただの自己満足だ。
“測れる投資”だけを選べ──今すぐマーケティングに資金を投入せよ
誤解してほしくない。
私は社会貢献をしたいというあなたの心意気を否定しているわけではない。
社会貢献──それは「売れる仕組み」を構築した後に、初めて意味を持つ施策だ。
企業にとって本当に優先すべきは、“会社を生かす”こと。
まず、売上を作れ。まず、市場に見つけられろ。
そのために、今あなたが取るべき行動は明白だ。
✔︎ ホームページを充実させ、訪問者からの問い合わせを増やせ
✔︎ 動画広告で自社技術と価値を見える化し、顧客を惹きつけろ
✔︎ マーケティングオートメーション(MA)で見込み客を教育せよ
✔︎ ブログや技術資料の検索順位を上げ、見込み客の流入を増やせ
これらの施策には共通点がある。
それは、“測れる”ということ。
「いくら投資して、いくら回収できたか」──この問いに、明確に答えられる。
つまり、経営判断として、“あり”か“なし”かを明確に評価できるということだ。
一方で、社会貢献活動はどうか?
KPIはない。問い合わせにつながったか?売上額がいくら増えたのかも測定不能。
そもそも、社会貢献活動には“成果”という概念が存在しないのだ。
その場では気分がいい。褒められて、拍手もされる。
だが──1年後、何が残る?
何も残らない。
「企業の社会貢献活動は売上アップにつながるのか? それともつながらないのか?」
──そんなことは、誰にもわからない。マーケティングの専門家である私にも、だ。
なぜなら、それは“測れない”からだ。
だからこそ言い切れる。
効果がわからない施策には、絶対に金を使ってはならない。
成功したか、失敗したか、判断もできない。
そんなブラックボックスな取り組みに、どうやってPDCAを回すというのか?
答えは、回せない。だからやるべきではない。
マーケティングは、測れる。
測れるから、改善できる。
改善できるから、売上になる。
──そして、それが会社と社員を守る。
売上を作る仕組みこそが、社員と未来を守る唯一の盾だ
マーケティングの実行コストは、月5万円からでも始められる。
広告代理店と契約し、大規模なテレビCMを打つ必要は一切ない。
中小企業こそ、展示会出展・Webサイト改善・SNS更新・技術ブログ活用など、
身の丈に合ったマーケティング施策を打つべきだ。
しかも、それらはすべて「数字」で評価できる。
何に、いくら使って、どれだけの反応が返ってきたのか。
どこで、どれだけの見込客が獲得できたか。
──全てが“可視化”される。
これこそがマーケティングの本質だ。
「なんとなく良さそう」ではなく、「数字で勝負できる」からこそ、
経営判断の強力な武器になる。
その数字は、
営業活動を強化し、
商談の質を高め、
見込み顧客を顧客に変える。
そして、その先にあるのは──売上という“現実”である。
この“売れる仕組み”さえ手にすれば、
あなたの会社は社会に媚びずとも貢献できる企業になる。
なぜなら、売れる会社こそが、最終的に人も地域も救えるからだ。
だが、現実には“売れる仕組み”を手にしていない企業が多すぎる。
社会貢献活動をすることで、“いい気持ち”に浸り、
経営判断を先延ばしにしている会社が山ほどある。
──その一方で、静かに、だが着実に、自社マーケティングを磨き上げ、
見込み客を奪い、シェアを奪い、未来を切り拓いている企業が存在している。
あなたは、どちら側にいたいのか?
「社会のために」ではなく、「社員と会社を守るために」──
経営者であるあなたがやるべきことは、“いい会社”を演じることではない。
“売れる会社”を作ることだ。
売れる会社こそが、未来を守る“唯一の盾”なのだ。