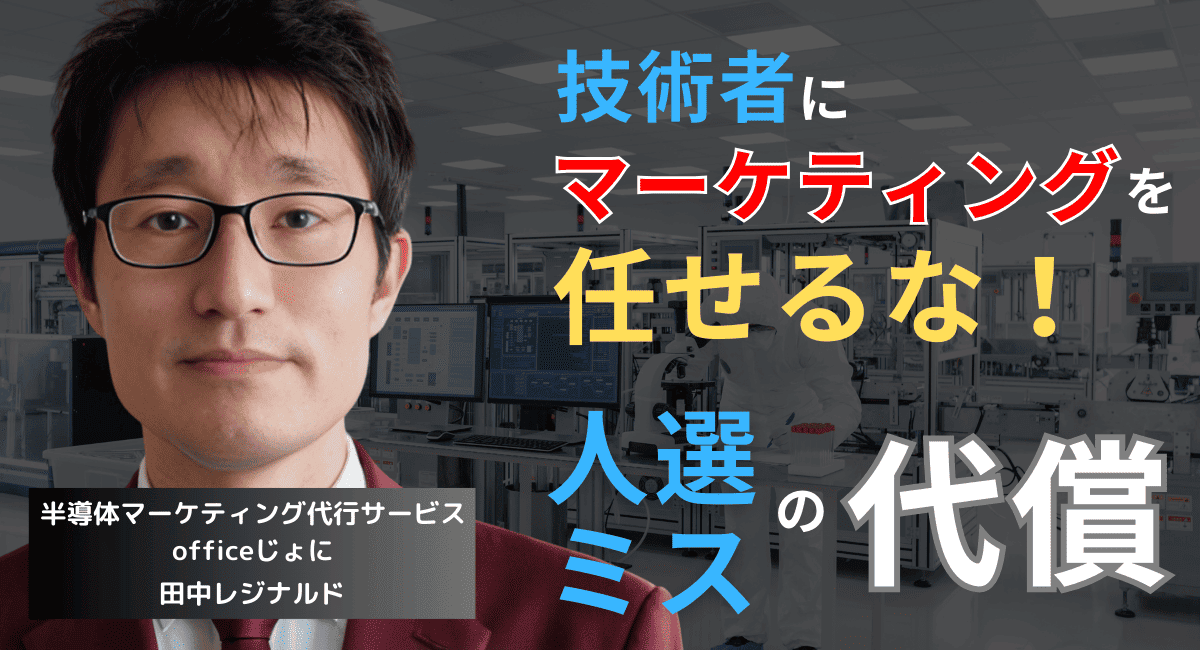もし、あなたが
「自社技術やスペックの詳細を語れる人材=マーケティング職に適任」
──そう信じ込んでいるのなら、今すぐその考えを捨てよ。
あなたの会社、こんな“人事判断”をしていないか?
・「彼は優秀なエンジニアだから、製品スペックを誰よりも熟知している。
だからマーケティングでも活躍できるはずだ」
・「彼はもう50歳を過ぎたし、現場を離れるタイミングだ。
管理職として“とりあえず”マーケティング部を見てもらおう」
・「彼女は技術職だけど、若くてSNS世代だし、インスタの更新くらいは
手が空いたときにやってくれるだろう」
──もし、こんなふうに「余った人材をマーケティングに回す」という発想が少し
でもあるのなら、すでにあなたの会社は“敗北のレール” の上を一直線に進んでいる。
マーケティングとは、“人が余ったから任せる部署”ではない。
成果を出すための適性と、勝ち筋を描く戦略がなければ、一歩も前に進めない──
れっきとした経営の主戦場である。
結論を言おう。
技術出身者にマーケティングを任せてはならない。
なぜなら、失敗する確率が圧倒的に高いからだ。
目次
技術者は“製品思考”で動く。マーケターは“顧客思考”で動く。
技術出身者の多くは、こう信じている──
「とにかく正確に」
「誤解がないように」
「すべての機能を網羅的に説明しよう」と。
つまり、
「製品スペックを誠実に、漏れなく、忠実に伝えること」こそが
“正解”だと信じて疑わない。
だが、マーケティングの現場で求められているのは、それではない。
顧客の“頭に残る伝え方”こそが、マーケターに必要な最大のスキルである。
🔍 マーケターとは?
単に製品やサービスを紹介する職員ではなく、「誰に、何を、どう伝えるか」を設計し、顧客の行動を促す“仕組み”を作る戦略家のこと。マーケティング活動を通じて、見込み客との接点を生み出し、成約へと導くのがマーケターの役割。
顧客が本当に知りたいのは、製品そのものの仕様ではない──
✔︎「この製品が、今抱えている問題をどう解決してくれるのか?」
✔︎「私の課題に対して、他の選択肢よりも、なぜこの製品なのか?」
✔︎「この会社と組むことで、自社ビジネスにどんな未来が待っているのか?」
この問いに対し、自分の言葉で、わかりやすく、熱を持ってWeb上で語れるか。
これこそが、優れたマーケターと、ただの製品解説者との決定的な違いである。
しかし現実には、技術出身者の多くが、
無意識に自社スペック・機能・技術の優位性ばかりを語ってしまう。
その結果、
「顧客にとっての意味」を一切伝えきれずに終わってしまう。
どれほど優れた技術であっても、顧客の心に届かなければ、
それは単なる“自己満足”にすぎない。
技術者がやりがちな“失敗マーケティング”──
その典型パターンを挙げよう
技術者にマーケティングを任せると、なぜ失敗が重なるのか?
理由は単純だ。彼らは“伝えるプロ”ではなく、“技術のプロ”だからである。
そのため、顧客目線ではなく、
「自分たちが伝えたいこと」を、技術者目線で一方的に発信してしまう。
その結果、見事にスベる。しかも、当の本人は失敗に気づかない。
では、実際にどんな“スベり芸”が現場で繰り返されているのか?
──ここから、現場あるあるの典型例を5つ、順番に紹介していこう。
✔︎ 自社ホームページに「製品設計図」や「保有設備」だけを延々と並べる
→ その瞬間、顧客の関心はゼロになる。「これはうちには関係ない」で離脱確定だ。
✔︎ ウェビナーで、60分間にわたり“製品スペックの読み上げ”を続ける
→ 技術資料の“音読会”を聞きたい顧客などいない。
YouTubeなら2分でスキップされ、ブラウザごと閉じられる。
✔︎ ブログ上で自社製品の強みを長々と書き、
「それで何が解決できるのか?」には一切触れない
→問い合わせに繋がるどころか、関心すら持たれない。
✔︎ 職員の“親しみやすさ”をアピールしようと、インスタに休日時の写真をアップ
→ はっきり言う。誰1人として初老男性職員のプライベートには興味を示さない。
✔︎ チームワークの良さを見せようと、社員全員で“恋ダンス”を披露
→ そんな時間があるのなら、自社製品を解説する動画を1本でもアップしろ。
それが見込み客にとっての価値だ。
これらはすべて、善意で起きる“事故”だ。
本人は「良かれと思って」やっているが、成果にはつながらない。
最悪の場合、こうしたアプローチが
あなたの企業のイメージダウンにつながることすらある。
マーケティングは“戦略”と“実行”の仕事である
マーケティングは、“感覚”でやっていい仕事ではない。
戦略を描き、現場で再現し、数字で成果を証明する──
完全に“ロジックと実行力”の戦場だ。
✔︎ どの市場に打って出るかを決め、
✔︎ 狙う顧客層を精密に定義し、
✔︎ 販売チャネルごとにセールスストーリーを構築し、
✔︎ 営業と連携して商談の歩留まりを改善し、
✔︎ 効果測定しながら、PDCAを愚直に回す──
これが、今の半導体マーケティングの“勝ちパターン”である。
その戦場に、
「彼は社歴が長いから」「彼女は若いから」などという理由で
人を送り込むのか?──
無理だ。断言する。
その瞬間から、あなたの会社のマーケティング費用──
年に数百万、いや数千万円が“音を立てて消えていく”。
広告費は燃える。
展示会では“誰も喜ばない技術力”を延々と語り続け、
インスタには可愛い絵文字が使われたキラキラ投稿。
営業資料は“アート作品”のように美しいが、売上には1ミリも貢献しない。
──そんな地獄のような“ムダ活動”を、10年、20年と続けさせるつもりか?
それが、あなたの経営判断だと言えるのか?
人選を誤る者に、マーケティングを語る資格はない
技術者には、“開発という名の戦場”で最高のパフォーマンスを発揮してもらえばいい。
プロダクトを磨き抜き、現場でしか得られない知見を武器に、競合を突き放す──
それこそが、彼らの真の舞台だ。
だが、マーケティングという“市場の戦場”では、求められる資質がまるで違う。
必要なのは、誰に、何を、どう伝えるかを描き切り、
数字という“結果”で経営に貢献できる人材である。
✔︎ 見込み客の“心の検索キーワード”を読める観察力
✔︎ 戦略を絵に描くだけでなく、現場で回せる実行力
✔︎ 顧客と市場の両方を見据えながら、未来を設計できる思考力
──こうした武器を持つ“仕組みの構築者”こそ、マーケティング担当にふさわしい。
あなたの会社の未来は、「誰をマーケティング担当に抜擢するか?」
──その、たった一つの判断で決まる。
その判断を誤れば、
どれだけ優れた技術があろうと、
どれだけ現場が汗をかこうと、
“売れない”という終わりなき地獄から、あなたの会社は一歩も出られない。
だが、正しい人材を配置すれば──
営業に頼らずとも問い合わせが舞い込み、価格競争の泥沼からも脱却できる。
そしてあなたの会社は、「選ばれる企業」へと変貌を遂げるのだ。
マーケティングの担当者選びは、人事異動ではない。
それは、未来を決める経営判断そのものである。