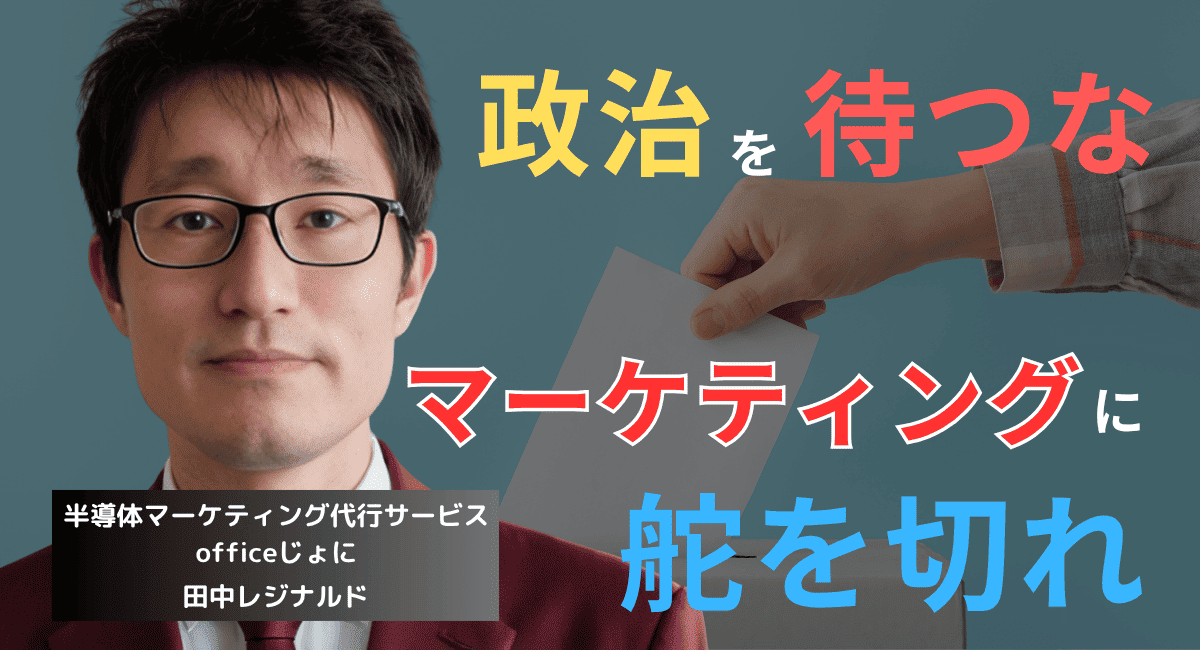企業の運命は、政治ではなくマーケティングで決まる
もしあなたが──
「政治家に会えば、ウチも少しは優遇されるかもしれない」
「補助金さえ出れば、来期はなんとか乗り切れる」
「国の支援が始まったら、ウチもマーケティングに取り組もう」
そう考えているのなら、今すぐその幻想を叩き壊せ。
あなたの会社を救うのは、議員バッジでもなければ、陳情の回数でもない。
ましてや、国会の空気や政局の風向きでもない。
Google検索で“1位”を獲る力──それだけが、売上を作る。
いま、中小の半導体企業の多くが、
“政治という宗教”に盲目的にすがっている。
選挙が近づくたびに、地元議員の顔色をうかがい、
新聞の取材に舞い上がり、経済産業省の資料を神託のように読み込む。
だが、それは「期待する者の姿勢」であり、
「自分で未来を創る者の行動」ではない。
仕掛ける者は、政治ではなくマーケティングを選ぶ。
支援を待つ者は、永遠に“外的要因”に振り回される。
マーケティングに舵を切る者は、“自力で市場を動かす側”に立つ。
この差こそが──
未来の売上、勝ち続ける企業、そして消える企業の分かれ道である。
政策を待った企業 vs Web戦略に舵を切った企業
例えば、こんな対照的なケースがある。
A社──地方にある中堅の半導体部品メーカー。
この10年、補助金の公募が出るたびに申請書を作り、
経済産業省の担当者にアポを取り、政治家との名刺交換に奔走してきた。
業界団体では重鎮扱いされ、委員会にも名を連ねている。
──だが、肝心の売上は横ばい。
結果として得られたのは、
たった1000万円の補助金と、地元議員との笑顔のツーショット。
そして、誰も読まない地方面の新聞記事。それだけだ。
一方、同じ規模のB社は違った。
営業部門と連携し、たった2週間でランディングページを立ち上げ、
ホワイトペーパーを連動させた。
さらに、YouTube広告・Googleディスプレイ広告を一点集中で投入。
その結果──毎月10件以上の「買う気のある見込み客」が、
自動的にWebから入ってくるようになった。
商談化率は60%以上。売上は前年比+240%。
今では商社を通さず、直販モデルで利益率30%超を確保している。
これが現実だ。
「政治が動くのを待つ企業」と「自分で動く企業」。
結果がどうなるかは、火を見るよりも明らかだ。
マーケティングは選挙ではない。
票の数ではなく、クリック数で勝負が決まる。
自社の裁量で売上を創る力が得られる
マーケティングとは何か。
──それは、「自社の意思で売上を作る力」そのものである。
たとえば、広告を回せば、その効果が数時間後に見える。
ホームページを1つ改善すれば、翌週の見込客数が変わる。
SEO(ブログ)記事を仕込めば、3ヶ月後の問い合わせ数が増える。
やるか、やらないか。
動くか、止まるか。
その差が、数字となって即座に返ってくる。
この「変化への即応性」と「結果の見える化」こそが、
マーケティング最大の武器だ。
一方、政治に何かを求めれば、どうなるか?
書類作成、ヒアリング、稟議、国会通過、交付決定…
数年単位の“時間泥棒”が、あなたの経営資源を奪い続ける。
あなたは数年後に手に入る“かもしれない金”に賭けている。
その間に競合は、今いる見込客を根こそぎ刈り取っている。
この時間差こそが、成長する企業と衰退する企業との
“決定的な分岐点”となっているのだ。
支援待ち企業から“売上創造企業”へ──その転換を今、実行せよ
改めて問う。
あなたの会社は、今、何に依存している?
✔︎ 政府の支援か?
✔︎ 商社の顔色か?
✔︎ 技術者の“努力”か?
✔︎ 営業の“根性”か?
──それらはすべて、あなたがコントロールできない「環境要因」である。
いわば、天気と同じ。晴れるかどうかを祈るような経営だ。
だが、マーケティングは違う。
広告の出し方も、予算の投下先も、メッセージの言葉選びも──
すべてあなたの裁量で決められる「自力要因」である。
✔︎ 自社Webサイトで、ターゲットの心に突き刺さるコンテンツを発信せよ
✔︎ 展示会で“名刺を配るだけ”の時代は終わった。動画で製品価値を3分で伝えろ
✔︎ SNS広告とSEO記事で、技術力の“見える化”を徹底せよ
✔︎ MA(マーケティングオートメーション)を導入し、営業活動を仕組みに落とし込め
もう、“支援を待つ企業”でいてはならない。
これからの時代、勝ち続けるのは、
“売上を自ら創る企業”だけだ。
そして、もしあなたがまだ──
「政治に期待している」「政治家とのコネが強みだ」と思っているのなら、
その瞬間、あなたは自らの経営権を“他人の都合”に明け渡していることになる。
その結果どうなるか?
選挙で選ばれた誰かのスケジュールと都合で、
あなたの会社の未来が左右される──そんな不条理な現実が待っている。
それは、企業として。そして経営者として──
最も愚かで、取り返しのつかない選択である。