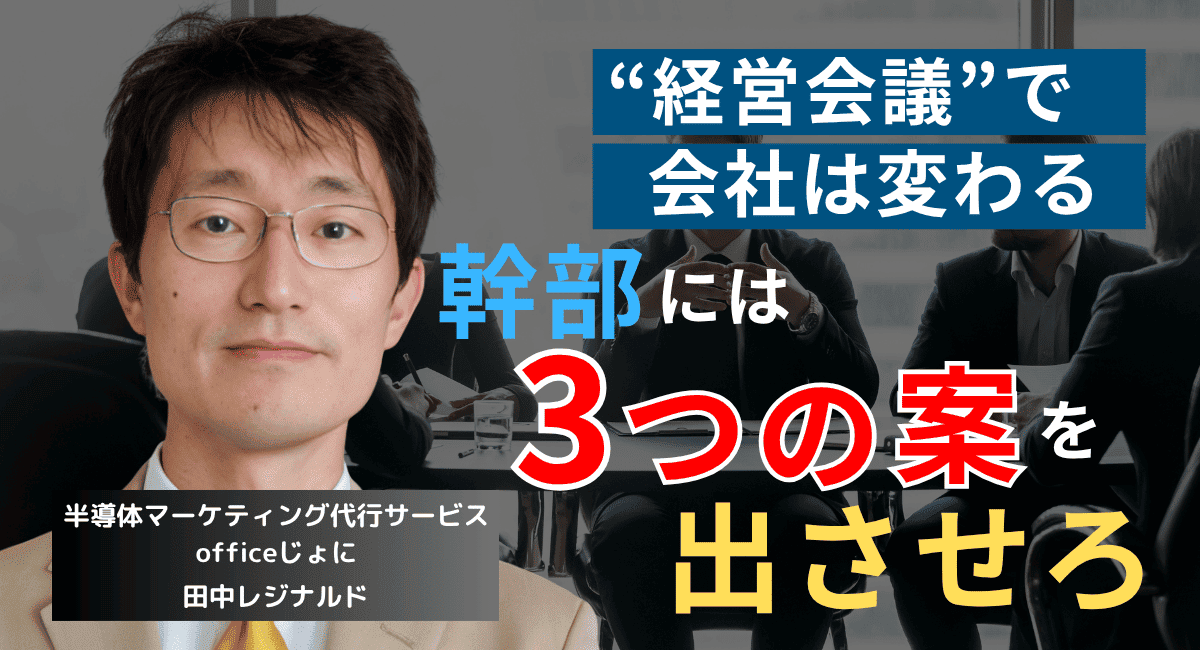もし、あなたが──
「売上が伸びないのは営業力が弱いからだ」
「営業マンを増やせば、会社は成長する」
「M&Aを繰り返せば、競争力は自然と高まる」
そう考えているのなら──その思考こそが、会社の成長を止めている元凶だ。
なぜなら、あなたの会社が成長できない本当の理由は、営業力の不足ではない。
ましてや、広告費が少ないとか、マーケティングの専門家がいないからでもない。
営業も、広告も、マーケティングも──
すべては、上層で決まった“戦略”に沿って動いているにすぎない。
そして、その戦略が決まる場所──それこそが、“経営会議”である。
経営会議とは、会社という組織を動かす“脳そのもの”である。
そのため、この“脳”が誤った指令を出せば、どれだけ現場の手足
(営業・マーケティング・開発)を動かしても、成果にはつながらない。
経営会議で誤った判断が下され続けるかぎり、
会社は延々と間違った方向へ進み続ける。
努力が成果に結びつかず、
むしろ裏目に出る構造から永遠に抜け出せなくなるのだ。
だからこそ、成長する会社と沈む会社を分ける最大の分岐点は──会議室にある。
あなたの会社の未来は、次の経営会議で
“どれだけ多くの解決策が提案されるか”にかかっているのだ。
会社の売上は技術力ではなく、経営会議で決まる
売上が伸びない──このとき、多くの経営者は「営業力の弱さ」を疑う。
そして、営業人数を増やし、マーケティング(広告)に全ての資金を投下する。
しかし、それでも結果が出ないのなら──見直すべきは「経営会議の中身」だ。
なぜなら、経営会議の質こそが、会社の成長を根本から左右しているからである。
そこで決まるのは、会社が「どこへ向かうか」という指針──つまり「戦略」だ。
もしその戦略がズレていれば、どれだけ現場が優秀でも、成果にはつながらない。
むしろ、努力すればするほど、誤った方向に深く踏み込んでしまう。
中小企業であれ、
中堅企業であれ、
大企業であれ、
売上は現場ではなく──会議室で決まっている。
たとえば──
ある製造装置向け部品メーカーが、経営会議で「テレビCMを打つ」と決めたとしよう。
予算は1億円。経営陣の満場一致で決定されたプロジェクトだ。
だが、少し冷静に考えてみてほしい。
その会社の顧客は、一般消費者ではない。
BtoBの法人──つまり、半導体製造装置メーカーや商社である。
日本国内における半導体関連人口は、せいぜい10万人前後。
そのようなニッチな市場に属する企業が、全国ネットでテレビCMを流す。
──果たして、それは正しい経営判断だろうか?
ここでの問題は、「営業力の弱さ」ではない。
最初に決められた“戦略そのもの”が、根本から誤っているのだ。
いかに優れたマーケティングチームが、最高のCMを作ったとしても──
それは、見込みのない株に、全力で投資しているようなものである。
✔︎ 売上アップにはつながらない
✔︎ 採用強化にも結びつかない
✔︎ 競争優位の確立にもなり得ない
つまり、経営会議で誤った判断が下されれば、
会社全体が間違った方向へとエネルギーを注ぎ続けることになる。
気づいたときには──組織の活力が完全に失われている。
会議では、各経営陣に「3つの解決策」を提示させよ
では、どうすれば、経営会議における
「意思決定の精度」を高めることができるのか?
そのカギとなるのが──
経営陣一人ひとりに“3つの解決策”を提示させるという仕組みである。
✔ 資料は、経営陣自身に作らせること
✔ 問題に対する解決策を、各自“3つ”用意させること
✔ 一人ひとりが、自分の言葉でプレゼンすること
この「3つの提案ルール」が、経営会議の質を飛躍的に向上させる。
では、なぜ「3つの案」なのか?
それは、どれほど優れた経営者であっても──
ひとつのアイデアだけで正解を導き出すのは極めて困難だからだ。
実際、世界トップレベルのコンサルタントでさえ、戦略の成功確率はわずか20%ほど。
つまり、たったひとつの選択肢しか持っていない状態こそが、
企業にとって最大のリスクとなる。
優れた将棋のプロが、複数の手を考えるように──
経営陣もまた、複数の解決策を持ってはじめて、「比較」と「洗練」が生まれる。
✔ CEO(最高経営責任者)には、3つの成長戦略を
✔ COO(最高執行責任者)には、3つの業務改善策を
✔ CMO(最高マーケティング責任者)には、3つの見込客獲得施策を
✔ CTO(最高技術責任者)には、3つの技術開発方針を
✔ CFO(最高財務責任者)には、3つの財務健全化策を
これが、本来あるべき経営会議の姿である。
選択肢なき議論は、ただの雑談にすぎない。
そして、部下に作らせたパワポをただ読み上げるだけの “朗読会” では──
変化の激しい市場で生き残るには、あまりに頼りない。
経営会議を変えれば、会社が変わる
経営会議は、「過去の出来事を報告するだけの場」ではない。
未来を描き、進むべき道を選択する“意思決定の舞台”である。
にもかかわらず、準備不足の経営陣が集まり、
たったひとつの案を曖昧に議論するだけ──
そんな会議で、どうして未来が拓けるだろうか?
✔ 経営会議で会社の戦略(方向性)が決まる
✔ 戦略(方向性)を誤れば、全社が一斉に“間違った努力”を始める
✔ だからこそ、経営会議そのものの“構造”を見直さなければならない
その改革の第一歩が──「3つの解決策」を経営陣に持たせることだ。
ひとつの正解に固執させず、異なるアプローチを考えさせることで、
思考が深まり、視野が広がる。
それにより、戦略ははじめて「比較」され、「検証」され、「洗練」される。
経営会議が変われば、会社の“軸”が変わる。
軸が変われば、戦略が変わる。
戦略が変われば、行動が変わり、成果が変わる。
つまり──
会社の未来は、“経営会議の再設計”からしか始まらない。
経営者には、経営者にしかできない仕事がある。
それは、経営会議を「思考と提案の競技場」へと変えることだ。
そのスタートラインは、こう宣言することにある。
「次回の会議では、必ず“3つの解決策”を用意してきてほしい」と。
ひとつの案しか出せない幹部に、未来を委ねるわけにはいかない。
選択肢が出揃って、はじめて戦略は比較され、そして磨かれていく。
これこそが──
競争の激しい半導体市場で、あなたの会社が勝ち続けるための、
唯一のマーケティング戦略である。