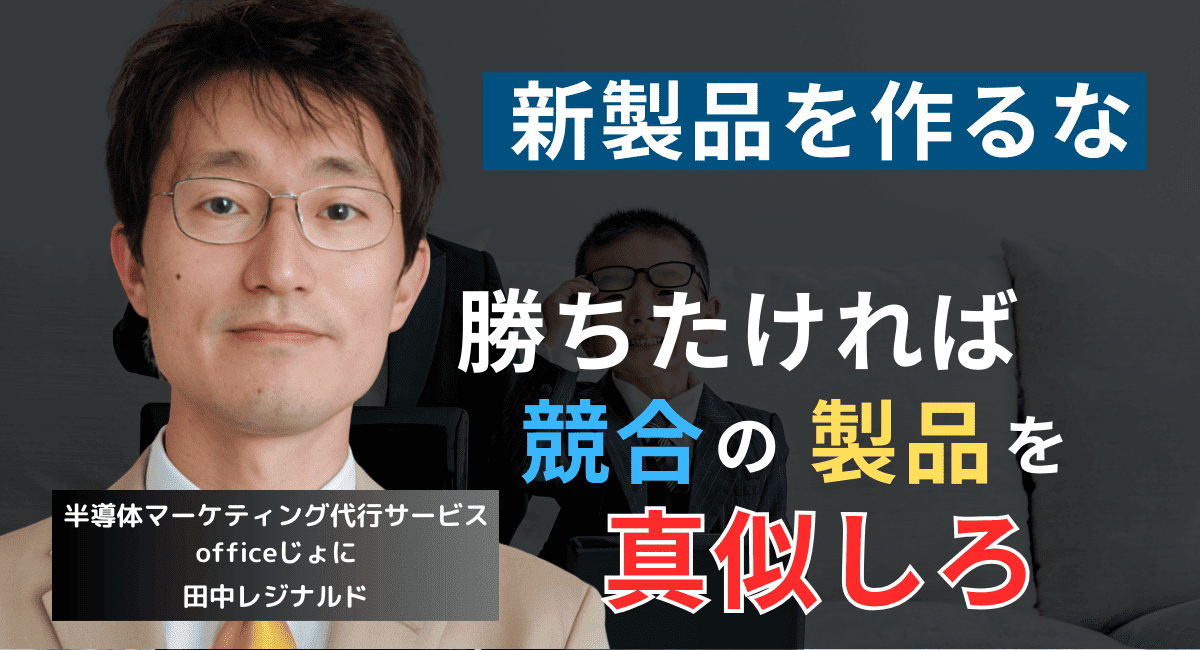もしあなたが──
「他社にない新しい製品を作れば、大ヒット間違いなしだ」
「うちだけの独自技術で、市場をリードしてやる」
「経営とはチャレンジの連続だ。ここで勝負に出よう」
──そう信じ込んでいるのなら、今すぐその考えを捨てろ。
それは、戦場に地図も持たず、丸腰で突撃するようなものだ。
いや、それどころか──
敵の位置すら知らないまま、爆心地に突っ込んでいく自殺行為に近い。
なぜそこまで言い切れるのか?
答えは単純だ。
売れる製品とは、「すでに売れている競合製品の“改良版”である」からだ。
完全な“新ジャンル”や“オンリーワン製品”は、
ビジネスの世界ではほとんどの場合、失敗する。
なぜなら、市場にまだ存在していないという事実は、
その製品に対する“明確なニーズ”すら、まだ生まれていない可能性が極めて高いからだ。
ところが、ここで多くの半導体社長が致命的な勘違いをしてしまう。
「技術が優れていれば自然に売れる」──そんな思い込みから抜け出せないのだ。
しかし、現実は残酷だ。
顧客は、あなたの“技術力”には1円たりとも払わない。
彼らが金を払うのは、ただひとつ。
“自社の課題を確実に解決できる”と判断した製品だけなのだ。
なぜ“新しい製品”は売れないのか?
では、あらためて問おう。
「市場に存在しない新製品」とは、一体どういう状態なのか?
それは──顧客がその製品の存在を知らず、
「欲しい」と感じたことすらない状態のことだ。
つまり、誰も欲しがっていない。
そして、それに気づかぬまま製品を持って営業に出れば──
待っているのは、想像以上に過酷な現実だ。
顧客は「それが必要だ」とまだ自覚していない
↓
そのため、営業は“説明”ではなく“説得”に追われる
↓
だが──導入実績はゼロ。証明材料もゼロ。信頼もゼロ
↓
結果、決裁権者はリスクを嫌い、社内稟議も通らない
つまり、どれだけ革新的な技術・製品であろうと──
顧客にとっては、“未知で不安なモノ”でしかない。
これは、真冬の日本海沿いで散歩している人に「新作水着」を売るようなものだ。
いくらデザインが洗練されていても、どれほど価格が破格でも、
その場で買う理由が1ミリも存在していない。
あなたが今、開発しようとしているのは──
「誰にも必要とされていない水着」かもしれない。
まず、その現実に気づけ。そこからすべてが始まる。
AppleもGoogleも「模倣」から始まった
あなたは、こう思っていないだろうか?
「AppleやGoogleのような“イノベーション企業”は、
ゼロから全く新しいものを生み出してきたのだ」と。
──もしそう信じているのなら、それは完全な誤解だ。
なぜなら、彼らのスタート地点は“模倣”だったからである。
Appleが参入した頃、パソコン市場はすでに先行企業がひしめく“戦場”だった。
マウス、GUI、ディスプレイ──そのどれもが、他社がすでに世に出していたものだ。
ゼロからの発明など、ひとつもない。
Googleもまた同じだ。
当時すでに存在していたYahooやAltaVistaの“改良版”として始まり、
その検索ボックスひとつ取っても、UIは既存モデルと大差なかった。
だが、彼らはそこで終わらなかった。競合の“失敗点”を徹底的に分析し、
「より早く・より正確に・より快適に」を、着実に積み上げていった。
つまり──「後発」であることを活かし、
それを“武器”に変えたことこそが、真の差別化だったのだ。
ここで結論を言おう。
「模倣」から始め、「最適化」によって突き抜けろ。
それこそが、後発企業が市場を制覇する唯一の王道である。
売れる確率を最大化したいなら、“類似品”しかない
中小半導体ビジネスの世界は──「天才の発明」が勝つ世界ではない。
「市場に求められている製品」が勝つ世界だ。
つまり、勝敗を分けるのは技術力ではない。
顧客に求められているものを、どれだけ的確に提供できるか──
それが成功の分かれ道だ。
もし、あなたの目的が「技術の探求」ではなく「売上」なのであれば──
もう迷う必要はない。やるべきことは、明白だ。
✔︎ 売れている競合製品を徹底的に分解せよ
✔︎ 機能・価格・ターゲット・販売導線を“丸ごと模倣”せよ
✔︎ その上で、「わかりやすく・導入しやすく・使いやすい」形に改良して売り込め
差別化? オリジナリティ?今は不要だ。
まず開発すべきは──「すでに金を払う気のある顧客」が欲しがっている製品である。
競合の模倣から始めろ。
そして、改良によって“勝者の座”を奪い取れ。
それこそが──
あなたが、このライバルだらけの激戦市場で生き残り、
勝ち続けるための、唯一のマーケティング戦略である。